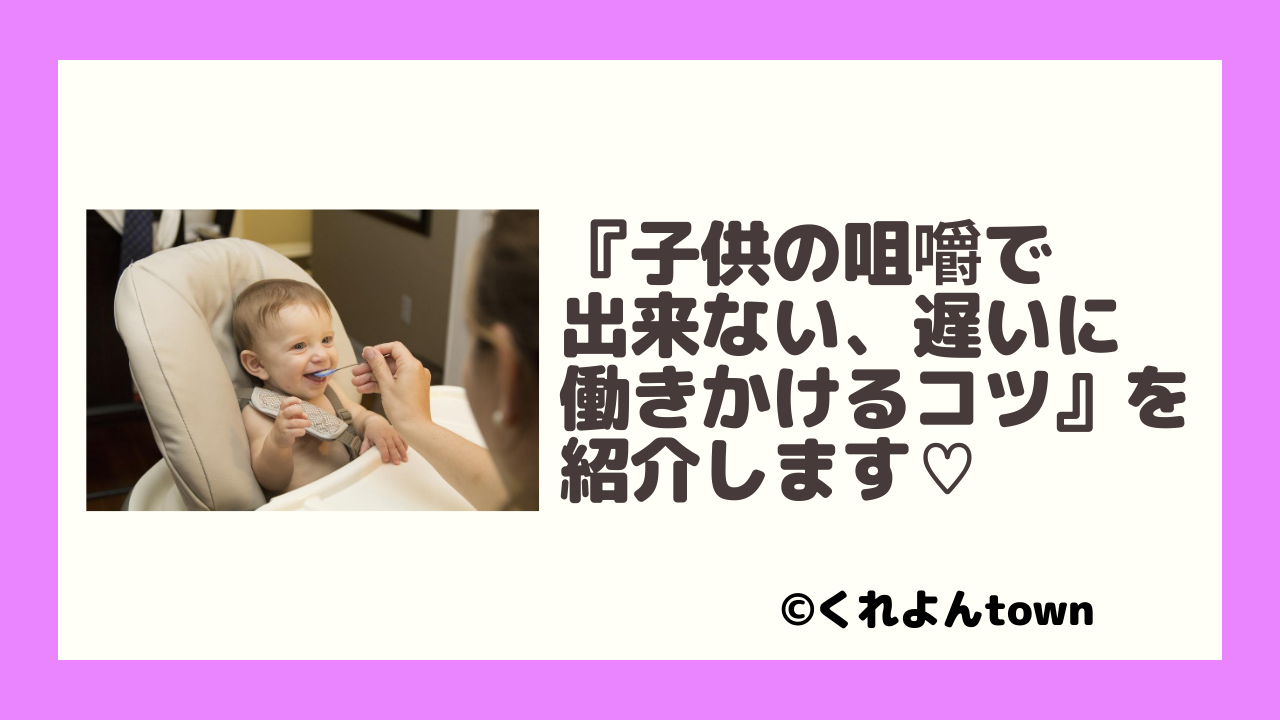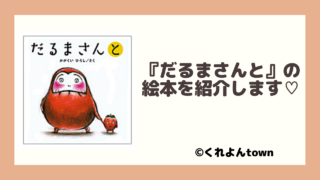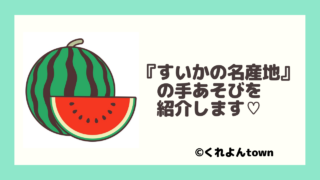こんにちは。ゆずこ(yuzuco_house)です。
咀嚼について、悩んでいるお母さん、お父さんがいると思います。
離乳食から初めてうまくいかない、どうしてと思うこともあるかもしれません。
子供の咀嚼について、どういう段階があって、どう働きかけるとよいのかをヒントになれたらと思い、書いてみました。
どの段階につまづいたのかな…と振り返って、やり直すことも出来ます。
ごはんを楽しく、食べることが大事なので、ヒントとして見てくれたらうれしいと思います。
子供の咀嚼について、どうして書こうと思ったのか?

出典:PAKUTASO|大きなお口でご飯をあーんする赤ちゃんのフリー画像
子供の咀嚼について、どうして書こうと思ったのか…。
以前子どもたちと一緒に過ごし、食事をしているときに、困りごとを発見しました。
その時に、悩みどう働きかけたら、食事を楽しく食べることができる、食べることがうまく出来るという経験を出来るのか、壁にぶつかったことがきっかけです。
悩みはアレルギーの勉強をしているときに、栄養士さんに相談しながら、働きかけてみたら改善していったので、その経験をふまえて、咀嚼の大切さを知ってもらえたらと思い、書くことにしました。
子供の咀嚼について
食事のことをしっかりと働き始めるときって、離乳食の頃からだと思います。
では、咀嚼についてみていきましょう。
ゴックン期
口を閉じてゴックンの練習の時期
ゴックン期の動画になります
口に入れて、ゴックンとして離乳食を食べていることがわかると思います。
まずは、飲み込む練習ですね。
モグモグ期
もぐもぐと口を動かし、食べ物をつぶして飲み込む練習をする時期。
- 食べ物は手づかみをして食べる。
モグモグ期の動画になります
モグモグと口を動かせれるようになったが、動画で見てもわかりますね。
口がモグモグと動いているか確認しながら、子どものペースに合わせて進めていってくださいね。
カミカミ期
奥の歯茎を使って食べ物をかむ練習をする時期
歯ごたえのものを食べることで、
- 噛む力をつける
- 咀嚼リズムをつける
カミカミ期の動画になります。
モグモグ期より少し口を動かしている時間が長くなったかな…と思います。
食材をすりつぶして、ゴックンする練習の時期なので、焦らず進めていってくださいね。
パクパク期
少しずつ大人に近い食事がとれるようになっていく時期。
固形のものを少しずつ食べられるようになり、大人の食事に近づいていっている感じですね。
うどんなど、短く切って食べやすくして、まだまだ配慮していくことがあるので、食べやすい大きさに調整してくださいね。
動画でもあった、野菜から出して、好きなものを後に出していくという援助も、子どもが嫌にならず食事ができるコツですね。
咀嚼の働きには、『ひみこの歯がいーぜ』がわかりやすい
ひみこの歯がいーぜを乳幼児の「かむ力」を育てる方法の情報から知りました。
ライオン歯科衛生研究所様から学ばせていただきました。ありがとうございます。
ひ 肥満を防ぐ
よく噛むと脳にある満腹中枢が働いて、私たちは満腹を感じます。
よく噛まずに早く食べると、満腹中枢が働く前に食べ過ぎてしまい、その結果太ります。
よく噛むことこそダイエットの基本です。
み 味覚の発達
よく噛むと、食べもの本来の味がわかります。
人は濃い味にはすぐに慣れてしまいます。
できるだけ薄味にし、よく噛んで食材そのものの持ち味を味わうよう、心がけましょう。
こ 言葉の発音がはっきり
歯並びがよく、口をはっきり開けて話すと、きれいな発音ができます。
よく噛むことは、口のまわりの筋肉を使いますから、表情がとても豊かになります。
元気な顔、若々しい笑顔は、あなたのかけがえのない財産です。
の 脳の発達
よく噛む運動は脳細胞の動きを活発化します。
あごを開けたり閉じたりすることで、 脳に酸素と栄養を送り、活性化するのです。
子どもの知育を助け、 高齢者は認知症の予防に大いに役立ちます。
は 歯の病気を防ぐ
よく噛むと唾液がたくさん出て、口の中をきれいにします。
この唾液の働きが、 虫歯になりかかった歯の表面をもとに戻したり、
細菌感染を防いだりして、 虫歯や歯周病を防ぐのです。
が がんを防ぐ
唾液に含まれる酵素には、発がん物質の発がん作用を消す働きがあるといわれ、
それには食物を30秒以上唾液に浸すのが効果的なのだとか。
「ひと口で30回以上噛みましょう」 とよく言いますが、よく噛むことで、がんも防げるのです。
い 胃腸の働きを促進する
「歯丈夫、胃丈夫、大丈夫」と言われるように、よく噛むと消化酵素がたくさん出ますが、
食べものがきちんと咀嚼されないと、胃腸障害や栄養の偏りの原因となりがちです。
偏食なく、 なんでも食べることが、生活習慣病予防にはいちばんです。
ぜ 全身の体力向上と全力投球
「ここ一番」力が必要なとき、ぐっと力を入れて噛みしめたいときに、丈夫な歯がなければ力が出ません。
よく噛んで歯を食いしばることで、力がわき、 日常生活への自信も生まれます。
どこかで聞いたことが語呂合わせでまとめられているので、咀嚼の大切さがわかりやすいですよね。
食事面だけではなく、健康面にも影響があるみたいなので、気をつけていきたいものですね。
咀嚼が出来ない、遅いにどう働きかけたらいいの?
大きくなって、咀嚼の問題に気づいて困っている子どもやお母さん、お父さんがいるかもしれません。
困っていても、働きかけで練習していくうちによくなることもあるかもしれません。
では、どう働きかけをしてみたらよいか見ていきましょう。
咀嚼が出来ない・丸飲みしてしまう
- 噛まずに飲み込んでしませんか?
- 柔らかいものを食べることになれていませんか?
1.離乳食のときに、「カミカミ、ゴックン」をしっかり覚えてないと、噛まずに飲み込んでしまうことがあります。
食べた気になれず、いっぱい食べてしまいたくなることも多いので、ゆっくり噛む→噛んだらゴックンする練習をしましょう。
2.咀嚼力がうまくついていないこともあるかもしれません。
柔らかい食べ物だけではなく、かためのせんべいなど噛んで食べることを促せるものを、おやつなどで食べてみましょう。
咀嚼が遅い・噛みだめをする
- 一回で噛み切れる量を口にいれてますか?
- 噛み切れずに前歯で噛んでいたりしませんか?
1.まずは噛み切れるように、一回量を一緒に確認して、食べる練習もしてみましょう。
意外と噛み切れないものもたくさん入れてしまって、ずっと飲み込めずにいるかもしれません。
2.奥歯に持っていくことが出来ずにいて、前歯でずっと噛んでいてすりつぶせなく、
飲み込めずにいるときもあるかもしれません。舌がうまく動かせずに奥歯に持っていけない場合は、
大人が苦しくないように奥に持っていく方法を知らせていきましょう。
※舌足らずで言葉がうまく話せない子に、たまに見かけます。
舌の動かし方を知らせていくと、少しずつ舌足らずがよくなることもあります。
子どもが吸いながら食べる、吸い食べ
- 食べているときに口を開きながら食べていたりしませんか?
- また、奥歯を使っていますか?
1.口を閉じながら食べれないと、音を立てて食べていたり、口の中にある食べ物をこぼしてしまったりします。
まずは、少しずつ閉じてたべる練習をしてみましょう。
※鼻が悪くて、口呼吸になってしまい、食べるときも口を開けてしまう場合は、耳鼻科などにいって鼻の通りをよくすると
いいかもしれませんね。
2.前歯で噛みとれるように、少し硬めのものから練習してみましょう。
前歯で噛み取ったら、奥歯に持っていくことを知らせてみましょう。舌がちゃんと動けているかも大切になってきます。
さいごに
ごはんを食べていく中で、咀嚼に悩んでいる子どもたちもたくさんいたことを知り、子育てや保育に少しでも役に立っててもらえたら、嬉しいと思います。
離乳食の大切さを改めて気づけたんで、今後離乳食について勉強しつつ、アウトプットしていけたらと思っています。